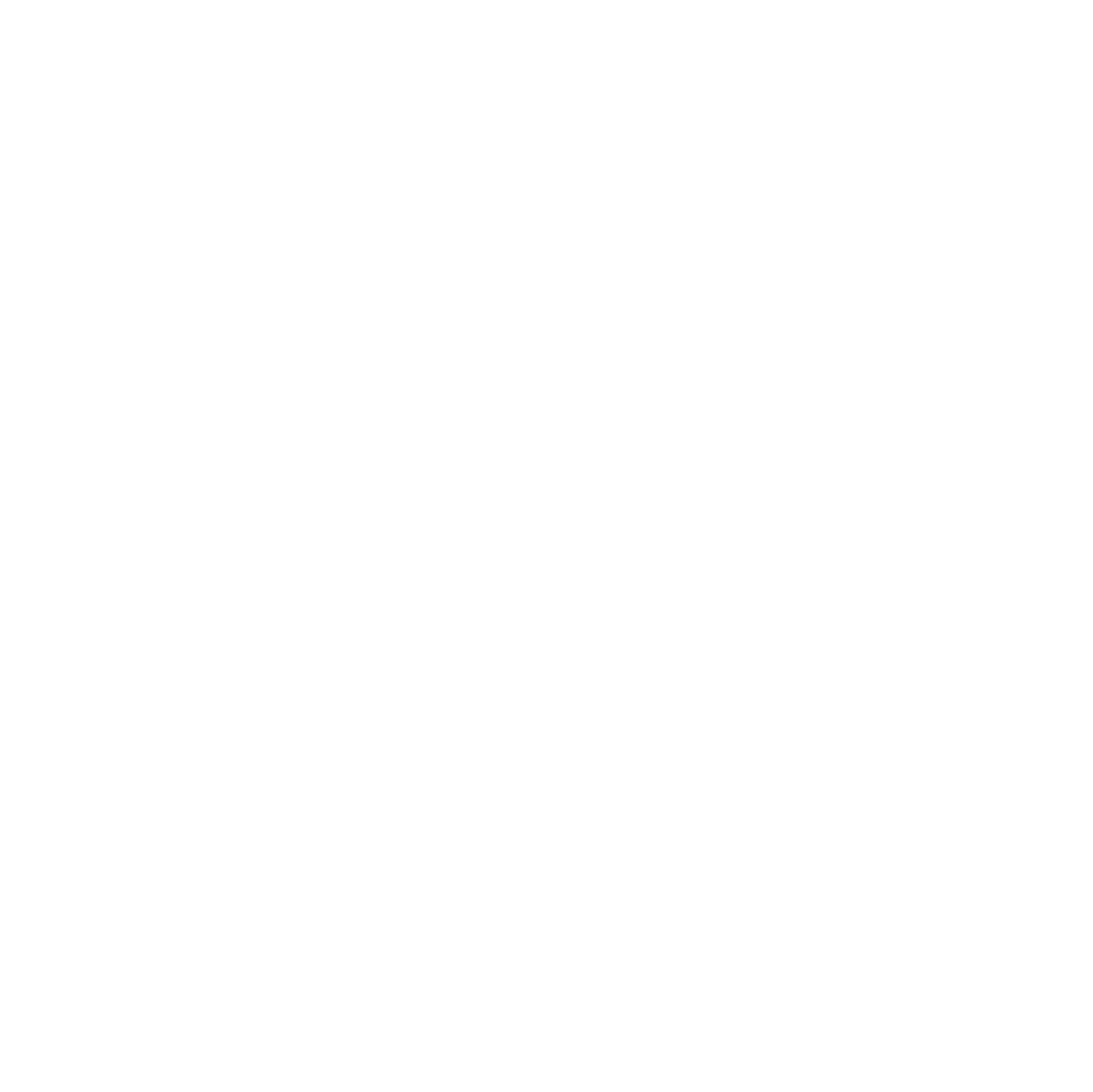生物資源科学科では、農林産業および環境保全の分野に貢献する人材を育成します。作物・園芸生産学、生物資源保全・植物保護科学、木質科学、山岳流域学、食料経済学など、農学の幅広い分野の講義や、静岡を中心に国内外の多様なフィールドを活用した実験・実習を通し、実践的な技術と知識を習得します。2年次後期からは「バイオサイエンス」または「環境サイエンス」のいずれかのコースに所属します。バイオサイエンスコースでは農林作物の生産や保護・利用の観点から、環境サイエンスコースでは持続可能な耕地利用や森林・都市・農村を含む流域管理の観点からそれぞれ専門性を高め、農学全体を俯瞰する力を養います。
教育・研究内容
カリキュラム(抜粋)
| 【教養基礎科目】
新入生セミナー,数理・データサイエンス,英語,キャリアデザイン 【教養展開科目】【専門基礎科目】 数学概論,物理学概論,化学概論,生物学概論,生物学実験,化学実験,物理学実験 【専門科目】 農学基礎論,生物資源科学基礎論,フィールド科学演習 |
||
前期 |
【専門科目】
分子生物学,植物生理学,土壌圏科学,園芸科学,作物学,基礎昆虫学,基礎生態学,森林水文学,生物材料科学概論,生物資源科学基礎実習 |
|
| コース分属 | ||
後期 |
【専門科目】 | |
| バイオサイエンス | 環境サイエンス | |
| 応用昆虫学,雑草学,植物医科学,食料経済学,木質材料学,生物材料接着学,園芸風土・文化論,果樹園芸学,野菜園芸学,バイオサイエンス実験Ⅰ,農場実習Ⅰ | 森林生態学,空間情報科学,保全生態学,木材化学,材料力学,緑地景観学,有機化学概論,木質機能科学,環境サイエンス実験 | |
前期 |
室内環境学,土壌微生物学,植物病理学,花卉園芸学,収穫後生理学,バイオサイエンス実験Ⅱ,農場実習Ⅱ,造林学,対話的探求 | 室内環境学,土壌微生物学,造林学,対話的探求,木質構造学,山地保全学,樹木生化学,実習・実験科目 |
| 研究室分属 | ||
後期 |
中山間地域振興論,植物育種学,プレセミナー,プレ卒業研究,森林生態学,空間情報科学,保全生態学,木材化学,材料力学,緑地景観学,有機化学概論,木質機能科学 | プレセミナー,応用昆虫学,雑草学,植物医科学,食料経済学,木質材料学,生物材料接着学,園芸風土・文化論,中山間地域振興論,植物育種学 |
| 研究室ゼミ,卒業研究 | 研究室ゼミ,卒業研究 | |
研究室一覧
バイオサイエンスコース
園芸イノベーション学研究室
松本 和浩 教授
園芸生理学研究室
富永 晃好 助教
応用昆虫学研究室
田上 陽介 准教授
応用昆虫学研究室
笠井 敦 准教授
花卉園芸学研究室
中塚 貴司 教授
共生進化生態学研究室
番場 大 助教
環境科学研究室
渡邊 拡 准教授
高分子複合材料学研究室
山田 雅章 教授
雑草学研究室
稲垣 栄洋 教授
植物圏微生物学研究室
橋本 将典 准教授
植物生産管理学研究室(果樹園芸学分野)
八幡 昌紀 准教授
植物病理学研究室
平田 久笑 准教授
農業経学研究室
柴垣 裕司 准教授
ポストハーベスト研究室
加藤 雅也 教授
ポストハーベスト研究室
馬 剛 准教授
木質バイオマス利用学研究室
小島 陽一 教授
木質バイオマス利用学研究室
小堀 光 准教授
野菜園芸学研究室
鈴木 克己 教授
野菜園芸学研究室
切岩 祥和 教授
環境サイエンスコース
環境微生物学研究室
鮫島 玲子 准教授
広域生態学研究室
薗部 礼 准教授
広域生態学研究室
王 権 教授
木質素材機能学研究室
田中 孝 助教
持続可能型農業科学研究室
南雲 俊之 准教授
住環境構造学研究室
小川 敬多 助教
森林遺伝育種学研究室
花岡 創 准教授
森林水文学研究室
江草 智弘 助教
森林生物化学研究室
河合 真吾 教授
森林生物化学研究室
米田 夕子 准教授
森林防災工学研究室
今泉 文寿 教授
生態学研究室
山下 雅幸 教授
生態学研究室
市原 実 准教授
造林学研究室
飯尾 淳弘 教授
造林学研究室
楢本 正明 准教授
哲学研究室
竹之内 裕文 教授
2023年度よりグローバル共創科学部(大学院は農学専攻)
環境社会学研究室
富田 涼都 准教授
農村福祉社会学研究室
太田 美帆 講師
分子進化・情報生物学研究室
堀池 徳祐 教授